この記事は、Julee Everett さんと Ryan Ripley さんによる「5 Tips to Increase your Emotional Intelligence as a Product Owner」の翻訳です。翻訳にあたって、Julee さんの承諾をいただいております。誤字脱字、誤訳がありましたらご指摘の協力をお願いいたします。
EQ ー 感情知性とは
プロダクトオーナーは、ビジネス、チーム、ユーザーからの期待値のバランスを常に取りながら仕事をしています。これは大変な仕事です。ときには報酬が儚く感じられますし、顧客が気まぐれだったりもします。でもあなたのチームが単にうまく機能していないだけかもしれません。ときには、自分が正しいことをしていると感じるかもしれませんが、チームはまったく反応していないこともあります。チームから最高の結果を得られていないと感じる場合や、チームがあなたと一緒に仕事をするのを好んでいないと感じている場合は、他の人があなたをどのように見ているかについて意識を高めることが、あなたにとって有益になるかもしれません。感情知性(emotional intelligence)として定義されているものです。以下、EQ と表現します。

EQ とは、自分の考え、発言、行動が他者に与える影響を認識し、その認識を利用して自分の振る舞いや人間関係をマネージメントする能力です。「頭と心のユニークな交錯」と表現されているのを聞いたことがあります。実際には、衝動制御と社会性を組み合わせて振る舞いを節制することです。
以下に挙げる EQ を高める5つのヒントは、EQ のスピーカーでありトレーナーでもある Scott Watson の仕事からヒントを得たものです。あなたが既にうまくやっていることを補い、チームの EQ と感情的な環境を改善するための戦術計画を立てる際に役に立つことを願っています。自分の振る舞いが他者にどのような影響を与えているかに着目することで、人間関係を変えることができ、キャリアにもポジティブな影響を与えることができることに気がつくかもしれません。
1. メンタル、時間、優先順位
自分のメンタルに着目し、時間と優先順位をどのようにマネジメントしているかをもっと意識しましょう。
新任のプロダクトオーナーと仕事をしていると、同じパターンをよく目にします。プロダクトオーナーは、嵐の中のボートのようにスケジュールに追われています。プロダクトオーナーには、日々のリズムがなく、息つく暇もなく、考えるゆとりもありません。ミーティングからミーティングへ走り回り、その日のすべてのやりとりから得たモノをチームに持ち込むのです。
感情は伝染します。すべてのことのバランスを取ることに注力してチームのイベントに参加すると、プロダクトオーナーのストレスや不安がチームに伝染していきます。ストレスや心配事を拾われてしまうことで、イノベーションや問題解決、ポジティブな相互作用には集中できなくなってしまいます。
時間と活動のマネジメントに関する情報源はたくさんあるので、ここでは触れません。宿題として、いくつかの記事を読んで、時間と活動のマネジメントのヒントを試してみてください。1日の中で時間をブロックして自分の主要な優先事項に集中できるようにしましょう。ユーザーにとっての価値を創造しましょう。限られた時間の中で、意味のある目標と説得力のあるビジョンだけを伝えることができれば、あとはパフォーマンスが高く信頼できるチームに任せることができるでしょう。
チームのエベントに参加する前に、まずは自分自身を中心に据えましょう。主要なスクラムイベントの15分前に時間を確保しておくと、心を落ち着け、達成したい目標に集中できます。自分に与えられた時間は、チームと連携できる可能性として反映されます。
ここで一旦立ち止まって、リラックスして、落ち着いて、集中してチームのイベントに参加するために準備していることを3つ書いてみてください。それらはあなたにとって価値があり、意味があり、適用しやすく、実用的であるべきです。
2. チームイベントに感情的要素を持ち込む
チームのイベントにあえて感情的な雰囲気を意図的にセットします。
リーダーとして、「チームにとって最も生産性が高いのは、どのような感情的な環境なのか?」と自問してみてください。ポジティブな振る舞いや高揚感、または、単によりよい個人的な交流を示すことで、場を暖めるための特別な意図を持ってチームとのそれぞれの相互作用できることを学びましょう。
1日を通して自分自身にいくつかの質問をすることは、ユーザーやステークホルダー、チームとの次の相互作用にとって感情的な寛容をセットするときに立ちに立ちます。これは、「なぜ(Why)」よりも、「どのように(How)」と「なにを(What)」の質問が効果的です。1日を通して自問自答する例をいくつか挙げておきます:
- チームが一貫性を持ってできる限り最適なパフォーマンスを発揮できるようにするために、自分ができる2つのことはなんだろうか?
- ユーザーのペイン(痛み)ポイントを理解し、最終的に革新的な解決策をつくるためにチームが知りたい2つのことはなんだろうか?
- このユーザー機能で、自分はチームからどのようなことを学べるだろうか?
- 自分たちは、このイベントをもっと楽しいものにするにはどうしたらいいだろうか?
1日の終わりに、「なにを(What)」で自問自答してみましょう。「今日うまくいったのは3つで、それはどうしてうまくいったのだろうか?」これによって、チームの風土を変え始める小さな習慣を検証することができるようになります。
ここで立ち止まって、朝や昼食時(午後の準備をする時間帯)と、1日の終わりに自問自答できる3つの質問を書き留めておきましょう。
1つのヒントとしては、これらの質問をスマートフォンのリマンダーとして設定しておくとよいです。これにより、あなたの EQ の向上を加速させる仕組みができるでしょう。
チームが既に素晴らしい日々を送っていると感じたら、「どうして自分は楽しく日々を過ごせているのか?」と自問してみましょう。常に成功を収めている場合は、プラクティスコミュニティ(CoP: Community of Practice)や地域のユーザーグループをで、他のプロダクトオーナーとコツやヒントを共有し、自分自身の振る舞いの向上させていきましょう。
3. 言葉だけでなく、身振りも
言葉で伝えることは重要ですが、身振り(ボディランゲージ)も同様に重要です。
私たちは、自分たちが使っている言語や自分自身の表情、それがチームにどのような影響を与えているのかをよくわかっていないことがあります。Scott Watson は次のように教えてくれました。
私たちは、一日中、顔を隠して過ごしている
Scott Watson
チームが何をみているのかはわかりません。そしてチームの身振りが伝えていることに常に気づいているわけでもありません。
ポジティブな言葉は、変化をもたらし、学習を強化できるということは、既にご存知のことでしょう。これを覚えておくのは難しいかもしれません。特に、扱いが難しいクライアントと一緒に仕事をしている場合や、規制やコンプライアンスの特性がある場合は、仕事をしていてもまったくのしくないことがあります。しかし、練習すれば、ネガティブな言葉をポジティブなソリューション指向のアプローチに置き換えることができるのです。信頼できるものでなくてはならないため、このような振る舞いの変化には、困難な自己評価と説明責任が伴うことになります。自分の強みだけではなく、ホットボタンやトリガーを理解するために、自己認識の訓練に投資をしましょう。
説明責任のテクニックとして、イベントのあとにチームの信頼できるメンバーからフィードバックをもらい、手助けをしてもらいましょう。私は一貫してこれをコーチングのキャリアにおうて使ってきています。それにより、自分の提供の仕方が柔らかくなり、自分の言葉やトーンが他の人たちに与える影響を意識するようになりました。私の説明責任のパートナーは、よりよい言い回し(フレーズ)を見つけてくれ、私の身振りと顔の表情や身振りに注意を向け流方法について手助けをしてくれます。イベントの直後に個人的なフィードバックセッションを行うことで、自分自身の意識が高まり、その後の振る舞いを変えることができました。
ここで一旦立ち止まって、クライアントやステークホルダー、そして自身が働いている組織について言ったことがあるネガティブな3つの言い回し(フレーズ)を書き留めてみましょう。ゆっくりと時間をかけて、これらの言い回しを置き換える3つの確実なものを見つけてみてください。
自身がネガティブな振る舞いに陥ってしまったら、明日は新しい1日であることを忘れないでください。これは打ち破るのが難しい振る舞いです。時間や注意、内省、説明責任を要します。
4. フィードバックする
価値があり、意味がある具体的なフィードバックを与えるようにしましょう。
具体的なフィードバックは、チームが個人的な赤んんを持ってプランニングして仕事に取り組むのに役に立ちます。偽って称賛をしてはいけません。あなたが中途半端な発言をすると、それは評価されず、逆効果になりかねません。「よくやりましたね(well done,)」や「お疲れ様(good job,)」と言ったり、最後に絵文字やスタンプ入りのメールを送ったり...。これは良い出だしにはなりますが、チームの成長にはあまり役立ちません。ポジティブなフィードバックをすることは大切ですが、本当につながっていたいのであれば、具体的なことを伝える練習をしましょう。
これを簡単に行うには、コメントに付加価値のある説明を付け加えることです。
例えば、「素晴らしいレビュー!」などという代わりに、ユーザー機能をリリースすることで解決する3つのペインポイントを説明することにより、先に進むことができます。このようなフィードバックによって、チームはあなたの期待をよりよく理解し、あなたは有意義な関係を気づくことができるようになります。
ここで一旦立ち止まって、過去3回のレビューとレトロスペクティブを思い返してみてください。以下についての回答を書き留めてください:「自身がチームに行ったフィードバックはどのようなものだったか?」、「フィードバックをもっと有意義なものにするにはどうすればとかったか?」
5. プレフレーミングとレビュー
プレフレーミングとレビューは、教育環境では一般的な指導手法です。クラスがこれから学習しようとしていることや学習を強化したりするときの意味や高揚感を生み出すためのものです。この2つのアイデアは、チーム環境でも教室と同じようにうまく機能します。
プレフレーミングとは、事前に何をするかを話し合うことです。仕事をする時間になったら脳が既に働いている状態にするという考え方です。これをビジョン設定やリファインメントセッションでチームに次のユーザー機能について話し合う価値に変換するのです。そして忘れないでほしいのは、何いうかだけではなく、どのように言うかだということです... 高揚感が持て、生き生きとしたものにしましょう。チームが一緒にソリューションをブレーインストーミングできるように、ユーザーにもチームに参加してもらって、特定のトランザクションがどの程度難しいのかを示してもらったりしましょう。それが新規のプロダクトの場合は、組織が次のユーザー機能に投資することを決定した理由を共有することで、関心を高める手助けになるでしょう。ユーザー機能に対して意味があり、測定可能な目標を一緒に作っていきましょう。
ユーザー機能が完成したら、チームで学んだことを少しひねりを加えてレビューします。このユーザー機能を開発している間に、チームがユーザーについて学んだことを少なくとも2つ話し合ってみてください。チームが技術的に学んだことに集中し始めたら、ユーザーについて学んだことに再誘導するのに役に立ちます。もしチームにそれができないのであれば、これはプロダクトオーナーであるあなたにとって、ユーザーとチームの間のギャップを埋める手助けをする機会となるかもしれません。
一旦立ち止まって、これからの次のユーザー機能について考えてみましょう。いくつかの高揚感と関心を開拓できそうな3つのセールスポイントを書き留めておきましょう。
まとめ
これらのヒントがあなたのチームの成功に役に立ち、あなたの EQ を楽しく探究できることを願っています。プロダクトオーナーとしての仕事を楽しめれば、チームはあなたと一緒に仕事をすることを楽しみにしてくれるでしょう。
あなたがチームのリスクを取り始めると、チームはあなたのリードに従い、チームの脆弱性が現れるかもしれません。これはプロダクトオーナーであるあなたと、スクラムマスターとで手を取り合って、仕事をするよい機会となります。一緒にハイパフォーマンスなチームに求められる安全な環境をさらに強化することができます。
5つのヒントを読んでいただいて、あなたは何か違うことをするでしょうか?私はそれを知りたいと思っています。
Julee Everett, PST より
真実を語り、技術を磨き、感謝の気持ちを表しましょう
本記事の翻訳者:
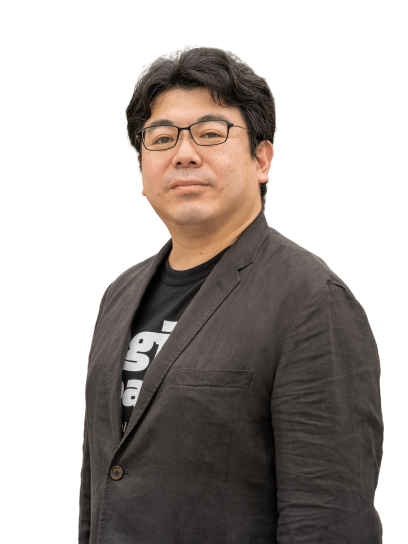
長沢 智治 - アジャイルストラテジスト
- サーバントワークス株式会社 代表取締役
- Agile Kata Pro 認定トレーナー
- DASA 認定トレーナー
認定トレーナー資格



認定試験合格
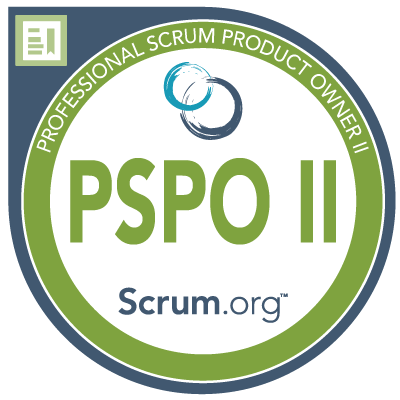
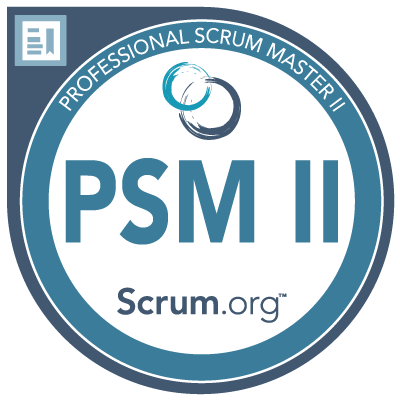
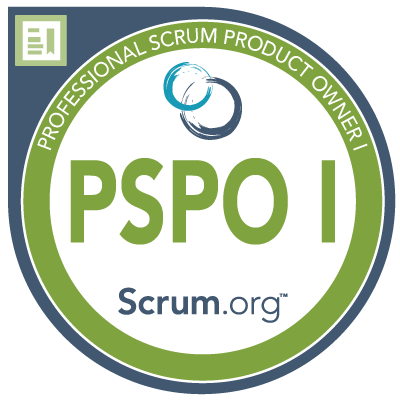
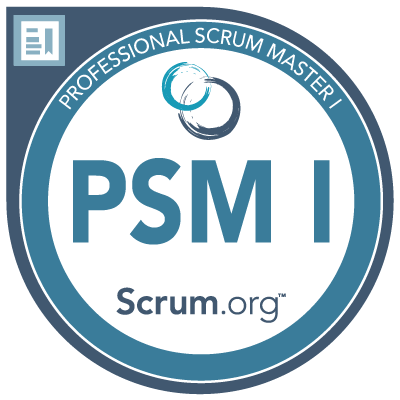


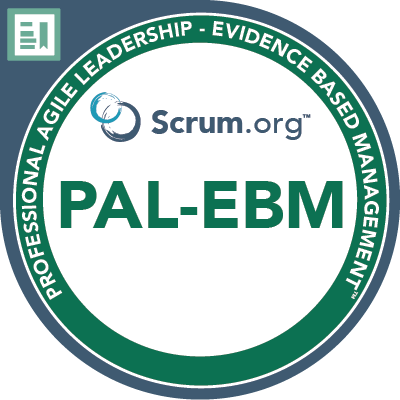
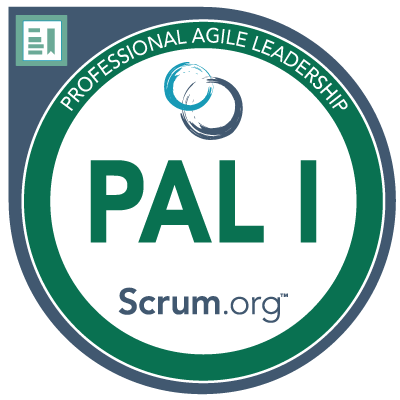

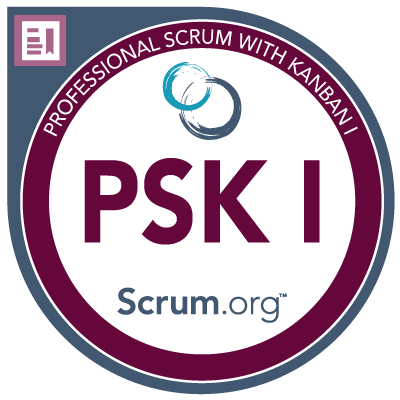
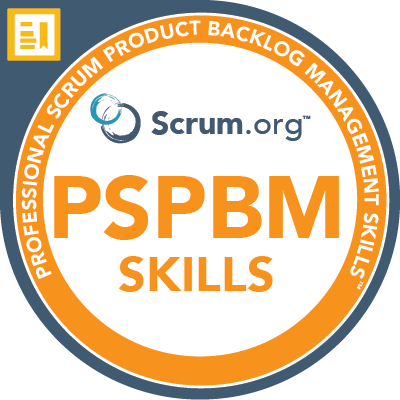
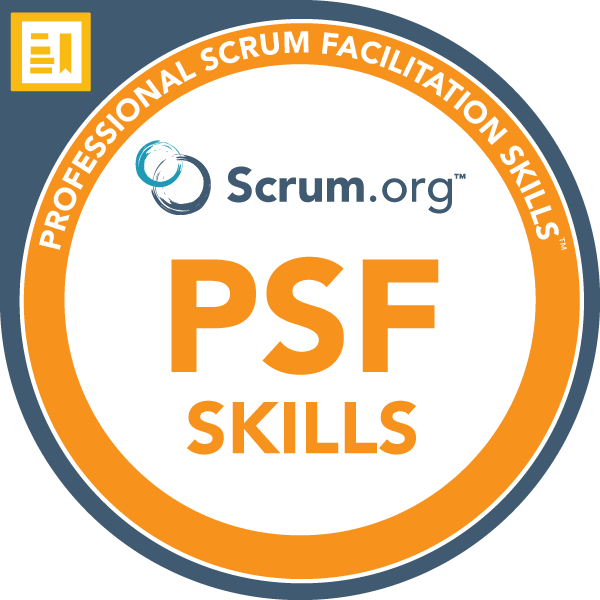
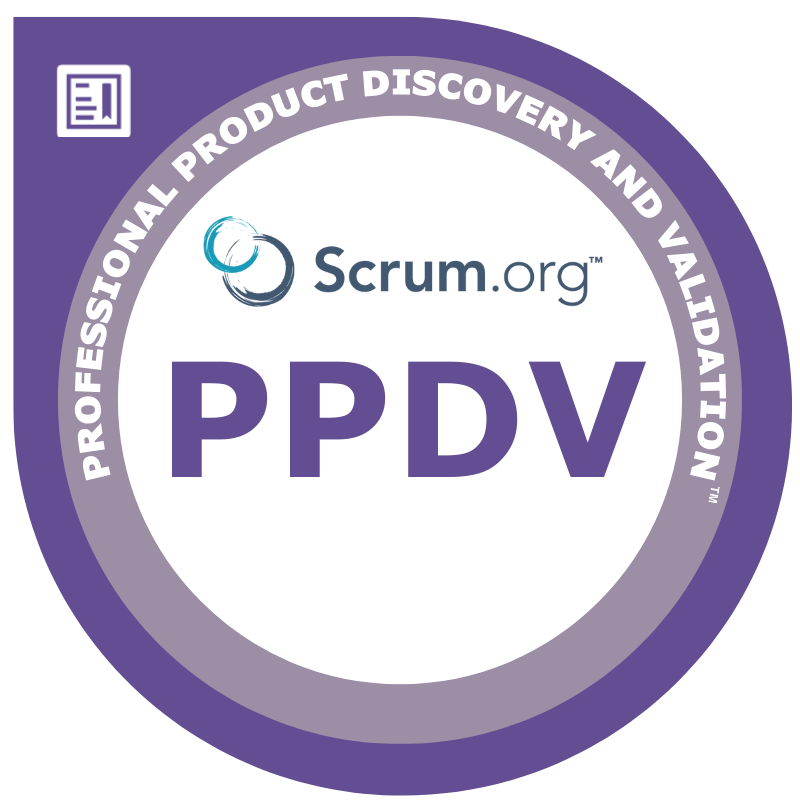
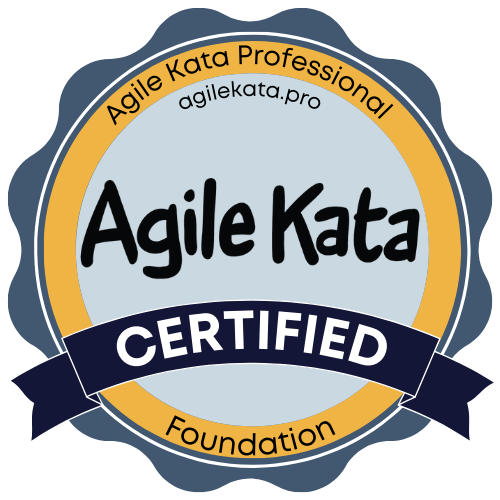



『More Effective Agile』、『Adaptive Code』、『今すぐ実践!カンバンによるアジャイルプロジェクトマネジメント』、『アジャイルソフトウェアエンジアリング』など監訳書多数。『Keynoteで魅せる「伝わる」プレゼンテーションテクニック』著者。
Regional Scrum Gathering Tokyo 2017, DevOpsDays Tokyo 2017, Developers Summit 2013 summer 基調講演。スクー講師。

