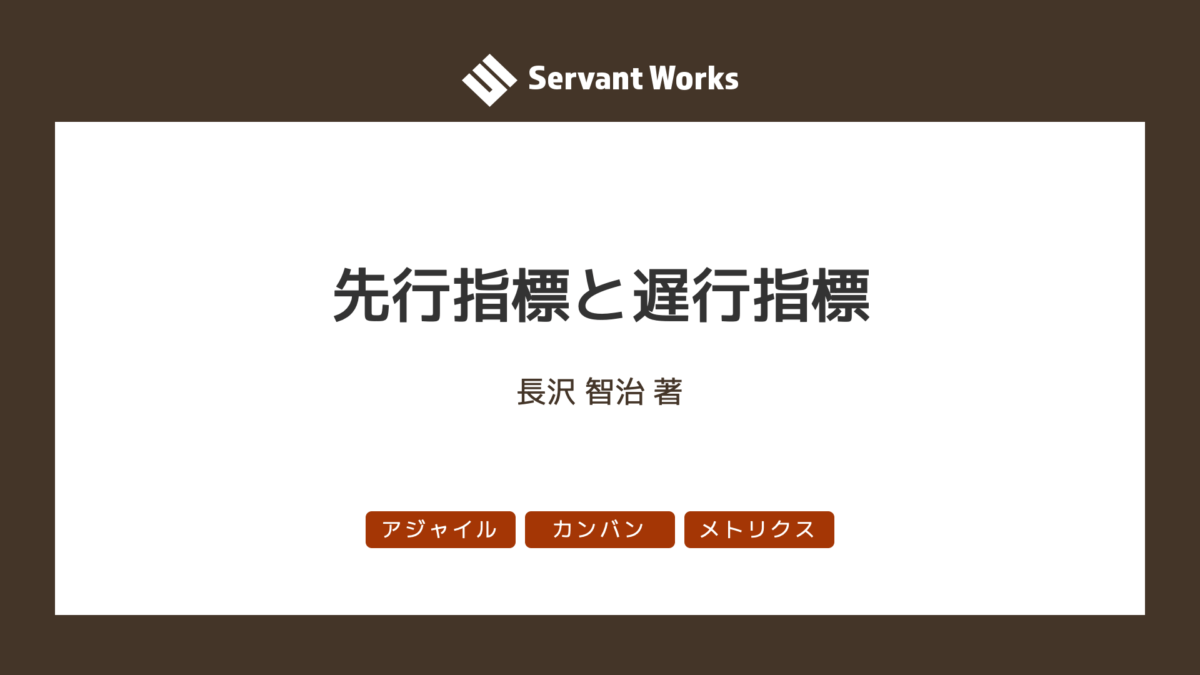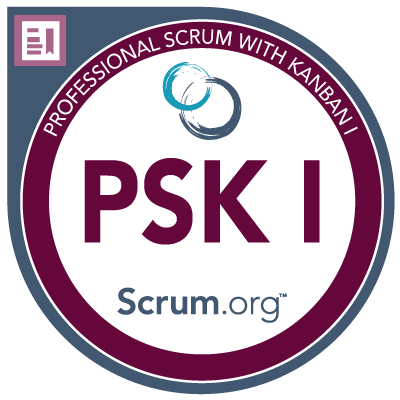
本記事の執筆者である長沢智治は、2021年1月にScrum.org認定のProfessional Scrum with Kanban (PSK) の認定試験に合格しております。
「計測できなければ改善できない」ということはよく言われていることですが、うまく計測できずに、計測疲れになることが多く見受けられます。実際には、計測する以前の問題であるので、指標の見定めの誤りであることが多いです。
そこで考えなけれならないのが、正しいものを計測しているかどうかです。
指標の考え方
指標とは、ものごとに価値をつける基準となる要素のことです。一般的には、これは客観的なデータで示されることが望ましいです。それについてはどなたも理解していることが多いです。しかし、それが大別すると2種類あることはあまり意識されることがありません。
2種類の指標
指標と成果(アウトカム)には因果関係があります。「成果を測る指標が必要」言うようにです。すなわち、成果にまつわる周辺因子から適切な指標を考えていかなければならないということです。
- 成果指標: 成果そのものを測る
- 成果予測因子: 成果の起因になるものを測る
成果指標
成果指標は、成果自体を測るための指標です。例えば、「売り上げ」など目標設定における「成果」そのものです。成果指標は、事業や活動の目標であるため、着目しやすく、わかりやすい という特徴があります。
成果予測因子
成果予測因子は、成果につながるものを測るための指標です。例えば、「売り上げ」という成果指標に対しての「MAU(月間のアクティブなユーザー数)」です。MAUが計測できれば、そこから売り上げが見えてくるといったような関係になります。すなわち、「売り上げ」を予測する一因だということです。成果予測因子は、それ自体が何かの目標に達するためのものであることが多いため、直感的にこの指標を測る意味がわからなかったり、見失いがちになりやすいです。また、成果指標に対して、成果予測因子を発見することも比較すると難しい傾向があります。
成果予測因子は、必ず「成果指標のために〜」という枕詞がつくことになります。成果予測因子だけで成り立つものではないことを理解しないと話がややこしくなります。先の例だと、MAU自体を成果指標にすることもだってできるわけです。カスタマーサービス部門の成果指標は、MAUであり、事業全体の成果指標は、売り上げであるという構図が成立するということです。
先行指標と遅行指標
このように、指標といっても、成果に対して直接的なものなのか、間接的なものなのかというのは考えなければなりません。なぜ成果指標だけでなく、成果予測因子を考えなければならないかと言うと、結果がでるまでの時間や影響がでるまでの時間が異なるからです。
これを理解しておくことはとても大切です。要は「測りやすいもの」と「測りにくいもの」があるのです。成果指標は成果が出てこないと測れないわけですが、測りかたは容易であることが多いです。売り上げは、結果がでるまでわかりませんが、誤りの少ない金額という結果で測るのは容易です。それに対して成果予測因子は、成果よりも測りにくい傾向があります。
また、成果指標は、結果が伴うので、軌道修正しにくい傾向があります。結果が出てしまっているので。それに対して成果予測因子は、これを測りながら軌道修正や改善を測りやすい傾向があります。
これは、一般的に、先行指標と遅行指標と呼ばれているものになります。
| 先行指標 | 遅行指標 |
|---|---|
| 成果予測因子 | 成果指標 |
| 改善が容易 | 改善が困難 |
| 計測が困難 | 計測が容易 |
| 成果に対するインプット | 成果に対するアウトプット |
もっともわかりやすい例が、ダイエットです。これは、DASA DevOps ファンダメンタルの認定研修でも例として採用されています。
筆者は、DASA DevOps ファンダメンタル認定研修の認定トレーナーでもあります。
- 先行指標: 摂取カロリーと消費カロリー
- 遅行指標: 体重
ソフトウェアとプロダクトでは遅行指標に関連する先行指標を見い出せるのか?
結論から先に書くと、「難しい」としかいいようがありません。作った分だけ価値が出る前提の製造/生産の場合は、売り上げやブランド力の先行指標として、生産量や労働時間/工場の稼働時間などを挙げることができます。ソフトウェアやプロダクトはどうかというと、たくさん働いたり、多くの機能を作ったら価値になるかというと残念ながらそんなに単純ではありません。よくあるSLOC(コード行数)、作業時間や人月、機能数、リリース回数が向上/改善したからといって顧客に対する価値が上がるとは言い切れないのです。従って、これらのアクティビティ(エフォート)やアウトプットは価値の指標にはなり得ないと結論づけてもいいでしょう(もちろんコンテキストに依ります)。
そこで拠り所なる計測指標はというと「アウトカム」になります。アウトカムはプラスになったりマイナスになったりするものなので、常にウォッチしておき傾向を見ておく必要があるものです。これらを見ながら、機能を作ったり、削減したり、実施する内容を工夫したり、組織的な能力を高めたりしていくしかありません。そのため、価値になるかは結果でしかないが、繰り返し実験を行いながらアウトカムという事実を傾向で追い続ける必要があるのです。
ちなみに、2014年にKen Schwaber氏がこれを指摘しており、そこから後述するエビデンスベースドマネジメント(EBM)のフレームワークが考案され、進化し現在に至っています。
エビデンスベースドマネジメント(EBM)
ビジネスアジリティのための意思決定とアウトカム(≒ 成果指標)の計測のフレームワークとしてエビデンスベースドマネジメントがあります。これは、スクラムと同様に経験主義(経験的プロセス制御)に基づくフレームワークです。ここでは「重要価値領域」として、以下のアウトカムの価値領域を定義しています。
- ビジネス価値
- 現在の価値(CV)
- 未実現の価値(UV)
- 組織の能力
- 市場に出すまでの時間(T2M) - すなわち「反応性」
- イノベーションの能力(A2I) - すなわち「効果性」
今や、EBMのフレームワークは、スクラムなど経験主義に基づくフレームワークのゴールや意思決定、投資判断(脱予算経営など)として用いられるとともに、プロセスやフレームワークに関わらずアジャイルであるかを判断する検査と適応の仕組みとして取り組む現場さんがグローバルだけでなく、日本でも増えてきています。
詳しくは、ぜひこちらにてキャッチアップしてください。研修や導入支援もしています。
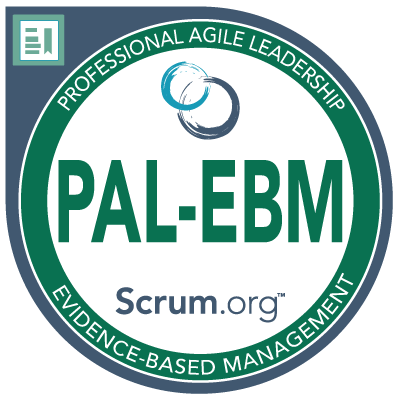
本記事の執筆者である長沢智治は、2021年にScrum.org認定のProfessional Agile Leadership - Evidence-Based Management (PAL-EBM) の認定試験に合格しております。
まとめ
指標には、先行指標と遅行指標があります。また、先行指標は、何かの遅行指標のために設定されているものです。従って、先行指標は、「<遅行指標>に対する先行指標である」と表現することが多いです。
先行指標と遅行指標を区別して、因果関係を明確にして設定できるようになると共通理解も促進でき、協働が促進されます。
本記事の執筆者:
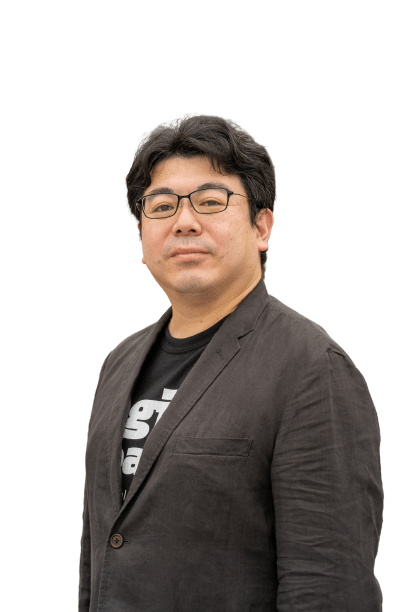
長沢 智治 - アジャイルストラテジスト
- サーバントワークス株式会社 代表取締役
- Agile Kata Pro 認定トレーナー
- DASA 認定トレーナー
認定トレーナー資格



認定試験合格
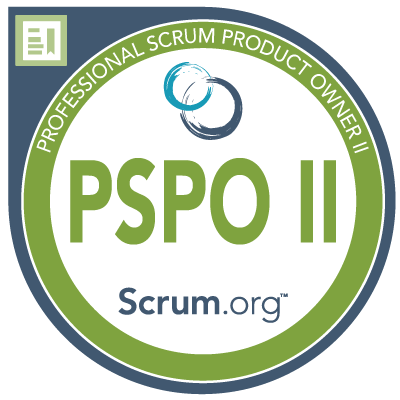
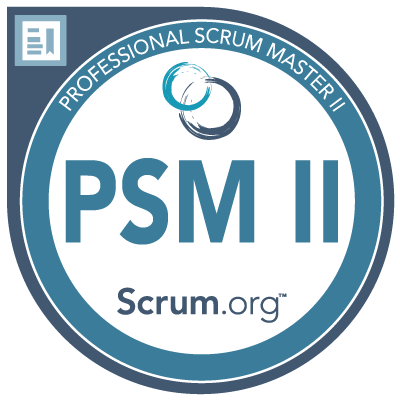
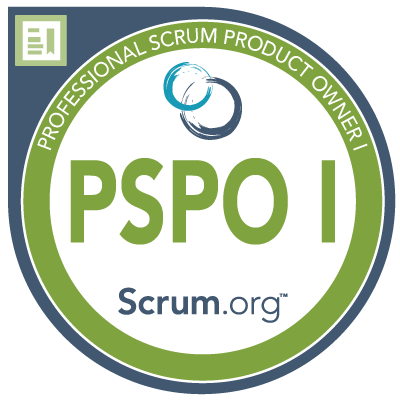
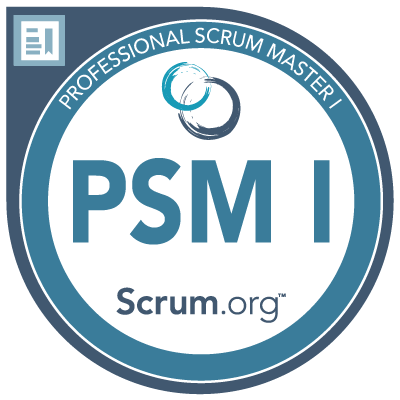


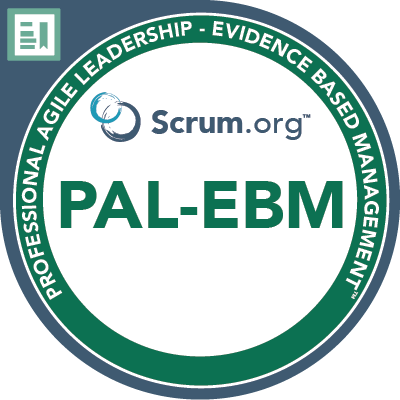
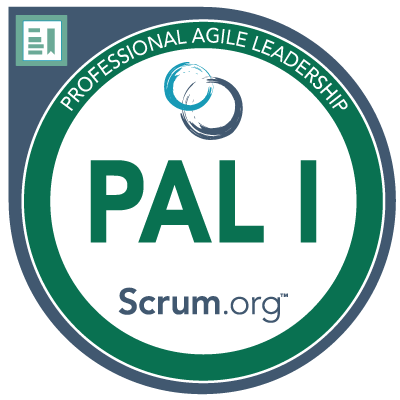

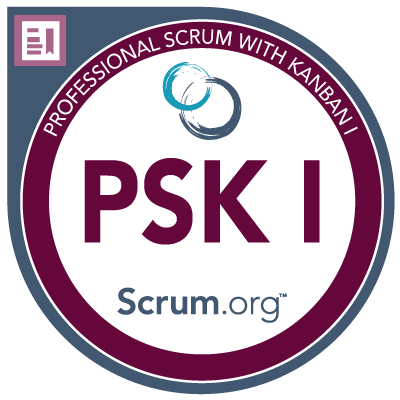
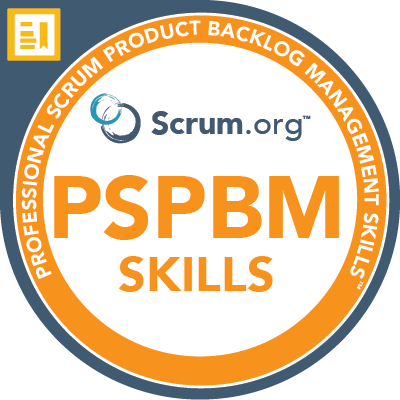
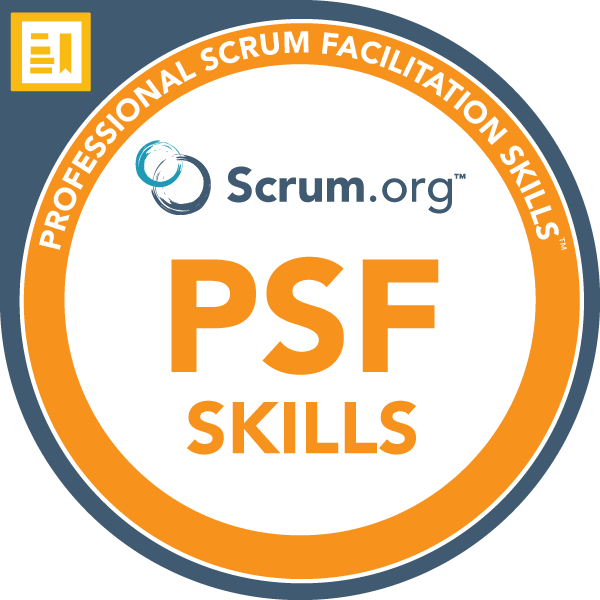
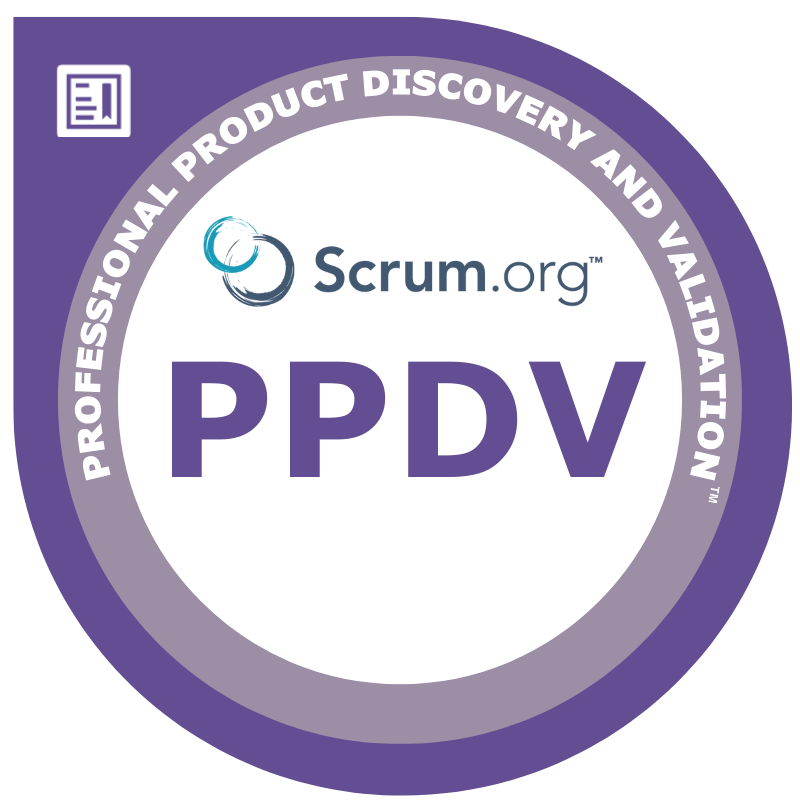
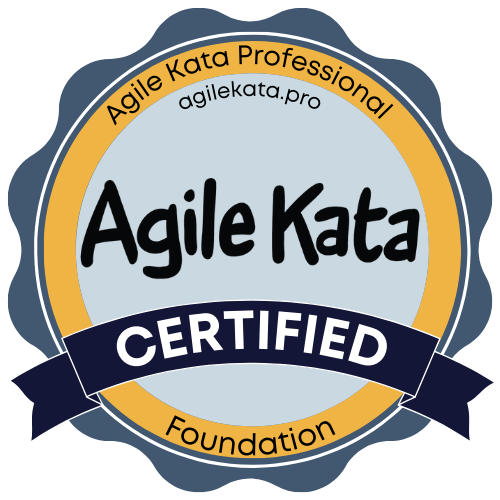



『プロフェッショナルアジャイルリーダー』、『More Effective Agile』、『Adaptive Code』、『今すぐ実践!カンバンによるアジャイルプロジェクトマネジメント』、『アジャイルソフトウェアエンジアリング』など監訳書多数。『Keynoteで魅せる「伝わる」プレゼンテーションテクニック』著者。
Regional Scrum Gathering Tokyo 2017, DevOpsDays Tokyo 2017, Developers Summit 2013 summer 基調講演。スクー講師。