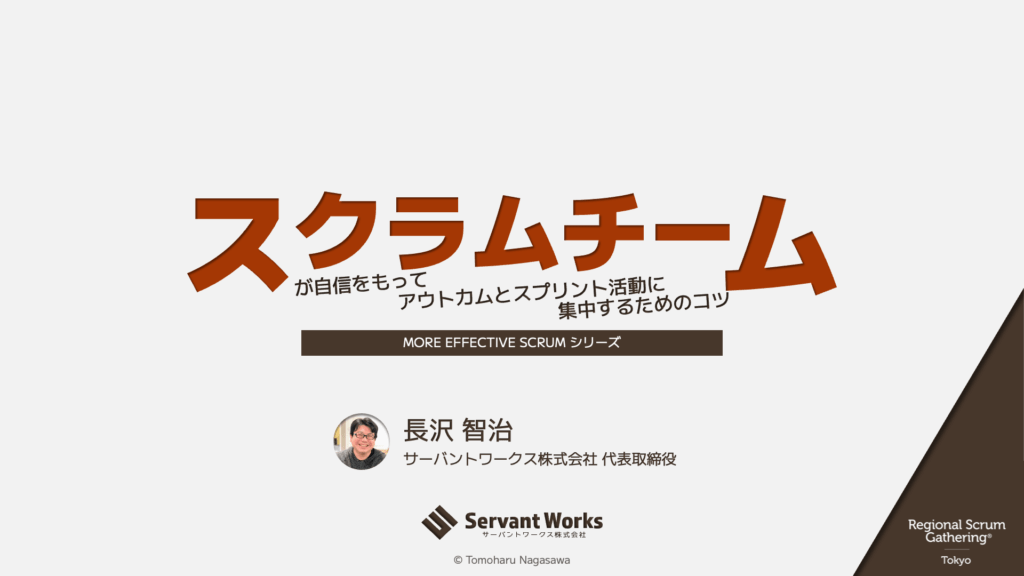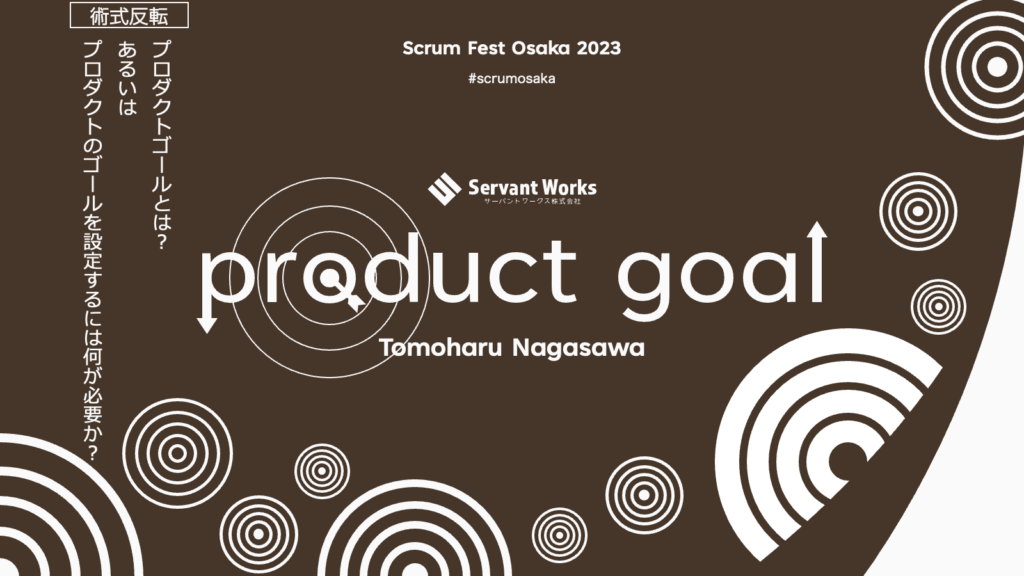本セッション資料は、RSGT2025 での講演したものです。
ご質問、再演などのご依頼はお気軽にご連絡ください。
RSGTでの講演資料
いただいたご質問への回答
- Q3段階のゴールとロードマップは同じ意味ですか?
- A
いいえ、3段階のゴールは、道筋のチェックポイントではなく、そこで見える景色にすぎません。遠位の方向性としてのゴール(EBMでの戦略的ゴール)と、近位の当面のゴール(EBMでの即時戦術ゴール)、その中間にあたる具体性のある目指すべき状態(EBMでの中間ゴール)を意識します。これらはその時にどうなっているかを、現在地視点で設定するより他にないため、不確実性が伴うものです(近位は具体的、遠位は不確実だが達成したいもの)。ゴールに近づけているかは、それぞれのゴールで描いた「景色」(状態、状況の変化)で測ります。これがアウトカムです。
それに対して、ロードマップは、比較すると、ある程度具体的な中継ポイントを予め示すことに近いです。具体的にやることがわかっている場合に有効で、ロードマップの中継ポイントに達する前提で活動するので、中継ポイントが確実性の高いもので設定することが多いです。
講演では山に例えましたが、よくあるロードマップを描く山のフレームワークは今回のゴール設定においては不適切ではないかと思います(上述の点において)。
- Qゴールにプロダクトの具体的な機能がでてこないのが気になります
- A
顧客アウトカムの視点で考えた時に、プロダクト自体がどうなっているかはあまり関係がありません。プロダクトの機能をブラックボックスとして捉えたとしても顧客がどんな課題を克服できているのか、どんな能力を得ているのか、その時に社会がどうなっているのかを描くべきです。そして、そのブラックボックスに自社プロダクトがあるということを想定・想像し、ビジネスインパクト、顧客インパクト、組織とチームのアウトカムを描きます。
このアプローチだと、実現方法に柔軟性が生まれるため、「予め計画した機能を期日までに完成させる」という硬直化したアプローチを取らなくてよくなります。状況変化に応じて実現方法は柔軟性をもつべきです。このアプローチならば、「作りすぎ」も防げます。また、プロダクトチームだけでなく、マーケティングチームやセールスチームで実施できることも盛り込めるため、プロダクトオペレーティングモデルにつながります。
- Q事実と推測や意見を区別するのは難しいと感じます。
- A
事実といっても、完全に客観的かつ正確性の高い事実に固執すると判断が遅くなることもあります。等身大で今、わかっていることから始めることをお勧めしています。確証が持てない根拠(≒事実)があったとしたら、その確証が持てるような「実験」を行えばよく、それはゴールに近づいているかの判断材料にもなるはずです。「実験」は、正しいことを確認する作業だけでなく、「間違っていること」を確認する作業に充てるのも重要です。そうやって「事実」を判断できるようになるのが大切であり、厳格な事実は必要に応じて求めればいいと考えています。
- Q遅行指標としてのアウトカムは計りにくいので、先行指標が重要なのですか?
- A
アウトカムは確かに結果指標に近いものであるため遅行指標となることが多いです。しかしながら、その先行指標を見出すのは非常に困難であり、複雑な状況下では特定できないことが多いでしょう。要するに相乗効果で結果が出ることになるからです。従ってアウトカムにつながるアウトプット指標やアクティビティ指標(エフォート指標)を計測することは極端にいうと諦めましょう。アウトカムは、一過性のものではなく、常に意識しておくべき指標です。従って、その傾向をみることを前提に設定してみてください。要するにアウトカムとは、プラスもあれば、マイナスになることもあるし、それらは相対的なものでもあります。
- Q経験主義は大事だが、足りない
- A
経験主義を疎かにして、スクラムやEBMを実践した末路はたくさん見てきました。経験主義をベースにしているフレームワークを用いるならば、経験主義の理解と実践は欠かせないものになります。
経験主義では、検査と適応を行うわけですが、スクラムでは、この機会をスクラムイベントとして提供しています。これは最低限に機会に相当します。スクラムのイベントで何を検査し、何を適応させるのかがわかっていないならそれはとても危険なことです。ゾンビスクラム、メカニカルスクラムになっているか検査してください。逆に、検査・適応しすぎてしまうことも気をつけてください(いわゆる改善ジャンキー状態)。価値を生み出す作業よりも検査・適応が楽しくなっていたら危険信号です。
経験主義は、行き当たりばったりでも、勘でもなく、科学的なアプローチです。